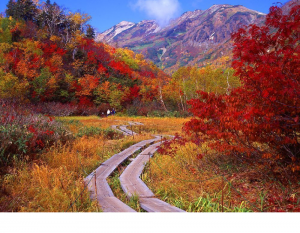北海道は独自地域分類を設け週末のみの60日は京都より厳しい条例です。

全国的に厳しい条例競争ですかね?
役人の保守的なところが出てます。
家主居住型・ホームステイ型っが対象外です。

北海道地域分類
(1)住居専用地域
(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル
(3)別荘地
住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内

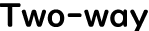




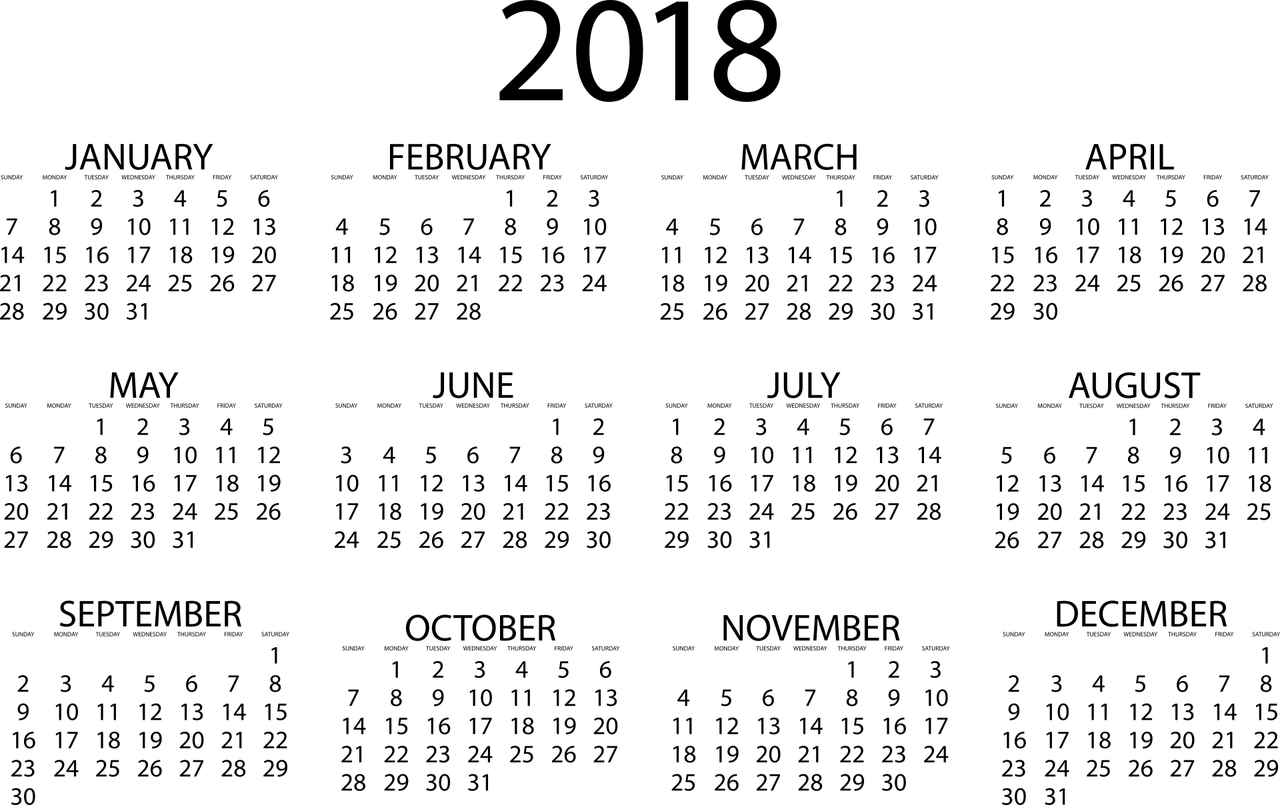







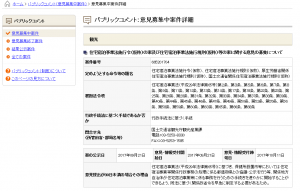
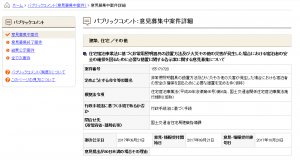
意見・情報受付期間は2017年09月21日〜2017年10月11日(21日間)
意見提出が30日未満の場合その理由 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、保健所設置市等においては住宅宿泊事業等関係行政事務の処理に係る都道府県との協議・公示を行う等、 関係地方自治体が住宅宿泊事業等に係る事務を行うための手続きを速やかに開始することができるよう、同法に基づく関係政省令を早急に制定する必要があるため。
法第18 条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、 住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
・届出住宅の規模等
・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨
・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。
・住宅の図面、登記事項証明書
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。 ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。
② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。
③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)
① 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。
② 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。
① 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。
② 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。
③ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。
④ 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。

京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。

jaxbartram / Pixabay
観光は国家にとって貴重な収入源となり、日本は観光立国を目指していますがどの様なビジョンがあるか不透明です。
国別では、
欧州各地で外国人観光客を排斥する動きが広がっている。
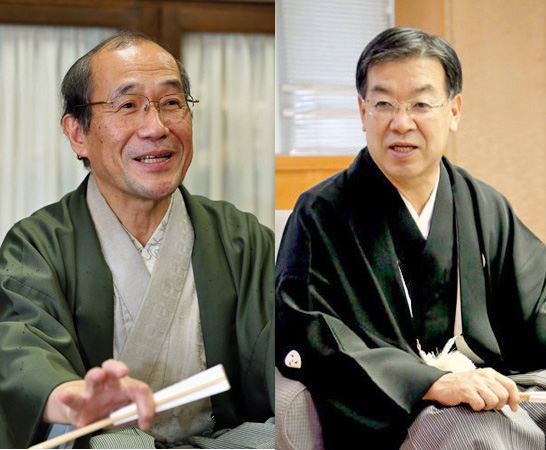
また日本の観光産業は内需型産業であり、京都も修学旅行を含め国内旅行に支えてられてきましたが、人口減少・高齢化により衰退の一途となりました。
国は人口減少にとても影響されやすい内需型ビジネスをインバウンドで喚起させるため観光立国を目指しビザの緩和や空港や港等のインフラ整備、ビックイベントである2020東京オリンピック承知、IR法案であるカジノ解禁へと色々な施策をとっています。
すると日本は島国であり外国人という対象がはっきりしない、分からないから周辺住民は不安になるのでしょう。もちろんルール違反は論外です。
京都新聞によると
「京都府の山田啓二知事は15日、府議会代表質問の答弁で、民泊の営業基準などを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の来年の施行に向け、民泊の規制や拡大について地域事情に応じて3分類で対策を進める考えを示した。
知事は答弁で、分類について▽生活環境の悪化防止や子どもの教育環境維持のために規制するべき地域▽滞在型観光の推進のため民泊の活用を希望する地域▽中間的な地域-の三つに分けて考える必要があるとした。「問題のある民泊施設の大半は京都市に存在していて大きな社会問題になっているが、他の地域は問題がそれほど出ていない。丹後では許可を受けた施設がほとんどで、無許可施設は1カ所しかなかった」との見方を示した。
府と京都市が行った実態調査によると、旅館業の営業許可を得ていなかったり実態不明だったりする民泊は、京都市では民泊仲介サイトに掲載された2702施設のうち2513施設に上った一方、京都市以外の府内では204施設のうち112施設にとどまった。
民泊新法の施行に合わせ、京都市は民泊規制を進める条例制定を準備している。山田知事は、特に新条例による規制を検討する京都市とは歩調を合わせていく方針を明らかにした。同時に、観光振興を望む地域では民泊の拡大を図る考えを示した。
府は今後、各地域の事情に合わせて規制や民泊拡大を進められるような条例の制定を目指す。
民泊新法は、現行法では宿泊施設を営業できない住居専用地域でも開業できるようにすると同時に、民泊の年間営業日数の上限は180日とし、さらに生活環境の悪化が懸念される地域では都道府県や政令指定都市が条例で日数を短縮できるとした。
府は、ホテルや旅館、旅行業者、観光協会、賃貸住宅などの各種団体が参加する府観光戦略会議民泊対策部会を22日に開き、各団体から意見を聞く。また観光庁が政省令案を近く公表して民泊の管理運営基準を示す予定で、府はこれらを踏まえて京都市や他の市町村と協議を進め、対策の中身を詰める。」