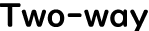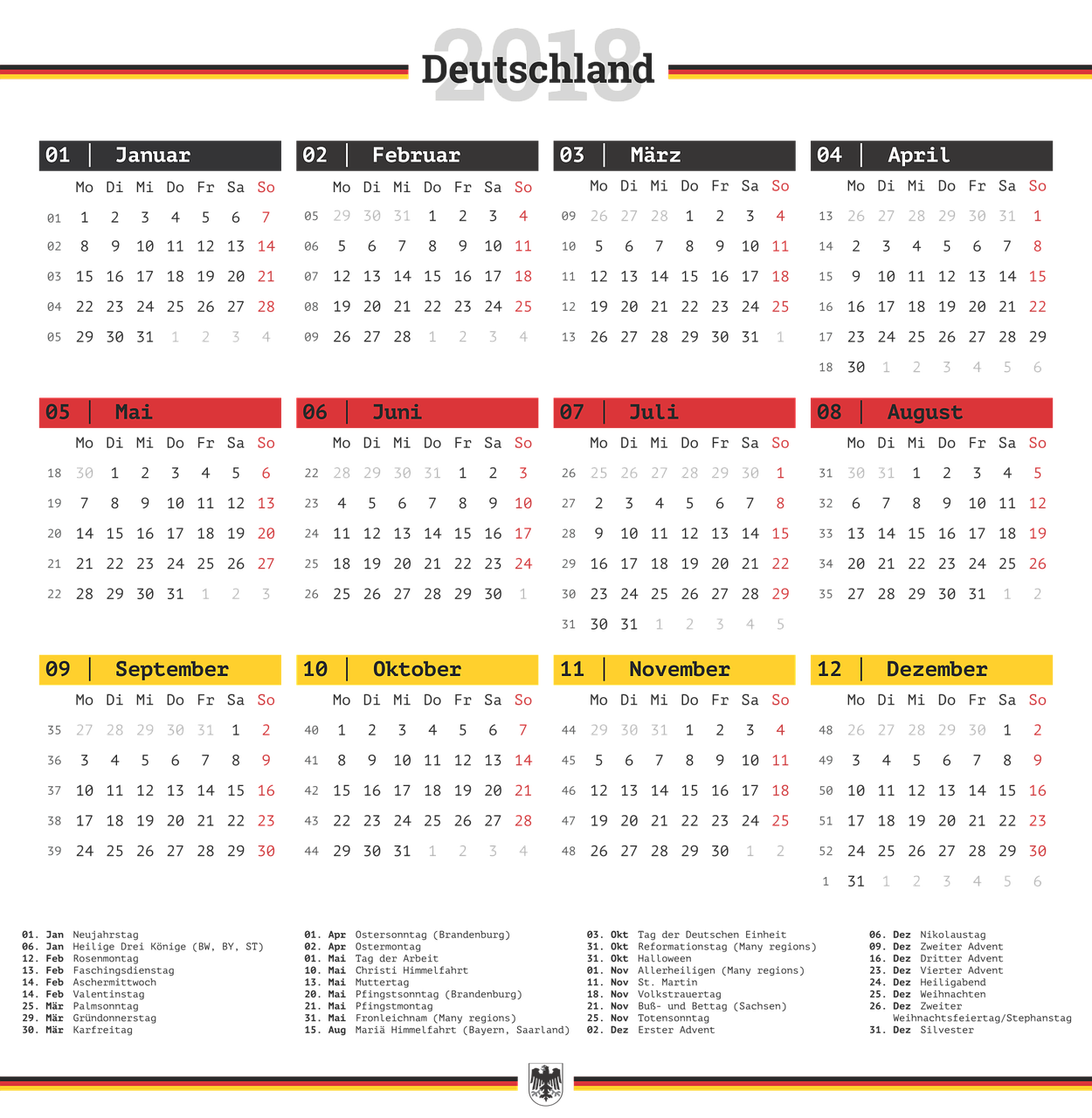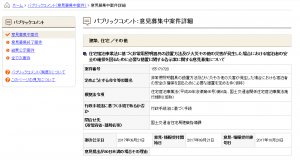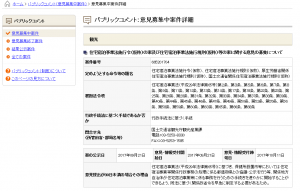民泊ルールの検討が始まってきました。来年6月15日施行に合わせるためには1~3月議会に提出しないと間に合わいません。

旅館業法改正も今国会で成立する予定で着々と民泊全国解禁に向けて進んでいます。
Airbnbに掲載されている民泊物件約5万室の内どの位が新ルールに適応できるのでしょうか?
共同住宅は区分所有法で管理組合設置が義務付られております。
民泊新法では管理組合の同意が必須となって9割ぐらいが民泊新法に適応不可能です。
また運営者も手間を避けてヤミ民泊になるか家具付き賃貸・マンスリーマンションを選択する方もいるでしょう。
ホテル業界は、民泊の入れ替わりになれることを望んでます。
2018年6月15日以降は1ヵ月以上が賃貸、1ヵ未満が旅館業か民泊新法・特区民泊となります。